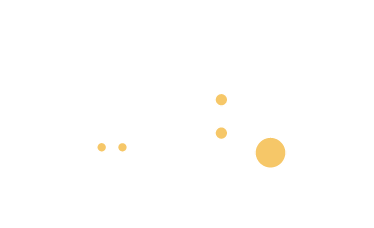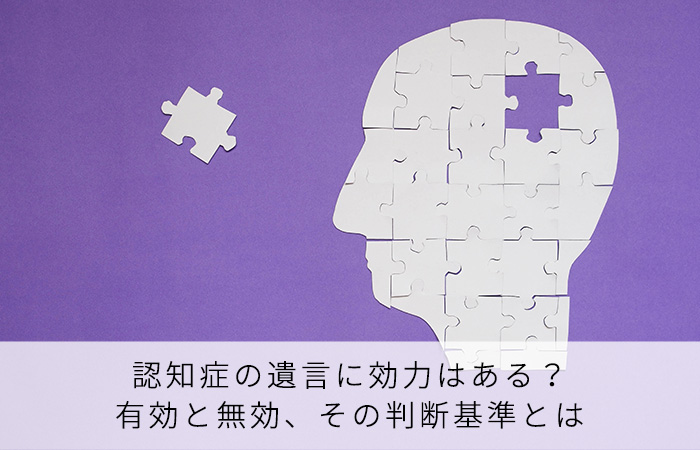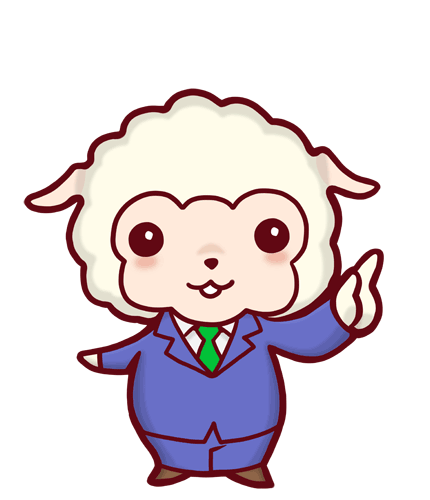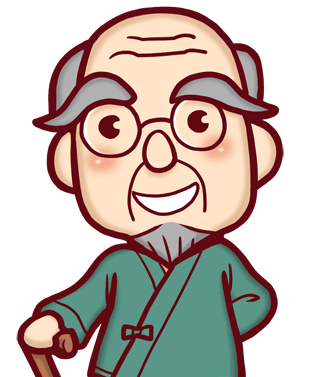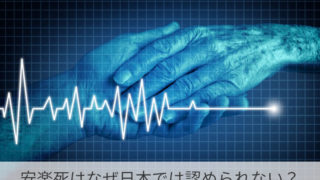高齢化が進み、認知症を患う人が増えています。
これにより、認知症になった家族が亡くなった際、故人が残した遺言が果たして有効なのかどうかでトラブルが持ち上がるケースも増加中。
実際にこうした事態に直面している方はもちろんのこと、終活当事者や高齢に差し掛かった親・親族を持つ人も、いざというとき無用なトラブルを避けるために「認知症の遺言の効力」についての正しい知識を持っておくことが大切です。
認知症はある程度の年齢になれば、誰がいつ発症してもおかしくない病気です。
だからこそ認知症という病気に対する正しい知識や、認知症にまつわる法律上の注意点などをしっかり押さえておきましょう。
もくじ
「認知症の人が亡くなった時の遺言の効力」にまつわる係争

最多なんですって。
2017年に経済協力機構が発表した調査によると、国内の全人口の2.33%が認 知症だそうです……
徐々にボケていくのは当たり前のこと。
歳を取ること自体を病気扱いされるようなもんで、失礼千万な話じゃな
超高齢化が進む日本では、認知症を患う人は今後ますます増加するとみられています。
最近、高齢者が「車を運転して事故を起こした」「徘徊して高速道路に迷い込んだ」「鍋を火にかけたのを忘れて火事になった」などのニュース以外にも、様々な場面で認知症が原因と思われる重大な事件、トラブルが頻発し、社会問題化しているのをご存知なのではないでしょうか。
終活関係で起こりがちなトラブルには「認知症になって亡くなった場合の遺言問題」があります。
故人亡きあとに残された遺言状の効力があるのか否かについて、利害関係のある人々の間で係争に発展してしまうのです。
終活がブームによって遺言を残す人が増える一方で、高齢化によって将来認知症を患う人も増加していけば、今後、認知症の遺言にまつわる係争はますます増えていきそうです。
このようなトラブルに巻き込まれてしまったらどのように考えるとよいのか、また今後、不要なトラブルを避けてしっかり遺言を残すにはどうすればいいか、順を追って考えていきましょう。
そもそも「遺言」ができる人って、どんな人

不要なもめごとが起こったりしないように、残した財産の配分などについて自身の意
向をしっかり書き残す方が多くなってきましたね
本題に入る前に、まずは「遺言」の定義について、おさらいしましょう。
【遺言】(いごん・ゆいごん)
被相続人の最終的な意思表示のこと。
遺言を作成することで、相続財産の継承をどのようにするか、遺言を書く本人の意思を反映させることが可能になる。
ただし「遺言」は、死の間際に親しい人に向けて私的なメッセージを書き残す「遺書」とは別物。
法的効果を持たせるには、法律にて定められた方式で作成されなくてはならない。
法律で定められた遺書の方式として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがある。
法的効果を持つ「遺言」ができる人について、民法では以下のように定められています。
- 15歳に達した者(民法第961条)
- 遺言能力のある者(民法第963条)
*遺言は、必ず本人が行うと定められていて、法定代理人や任意代理人が代行することはできません。
ひとつめの「15歳に達した者」は、年齢がこの条件に達していればすぐに法的効果があるかを判断できますが、問題になるのはふたつめの「遺言能力のある者」という点です。
認知症を患う高齢者が残した遺言の場合「遺言をした時、どの程度の判断能力があって、その遺言を自身の意思で行ったのかどうか」という部分が、係争のポイントになります。
認知症を患った人の遺言の効力

から自分の取り分を減らした」だの「誰かが認知症なのを利用してだまして遺言を作らせた」
といってもめるわけだな
遺言ができるのは「遺言能力のある人」です。
つまり物事を正しく認識ができ、判断ができる人でなければ遺言はできません。
この「物事を正しく認識し、判断する」能力に支障がある、認知症の人は、遺言を作成することができないのでしょうか。
ポイントは医学的に診断される「認知症」と、法的に判断される「認知能力」はイコールではないというところにあります。
認知症とは
「認知症」とは、認識したり、記憶したり、判断する力が障害を受けて社会生活を送る上で支障きたす状態をいい病名ではありません。
認知症の誘因にはさまざまなものがあるが「アルツハイマー型認知症」などがよく知られています。
医学的診断
医学的な診断は、医師によって行われます。
その際、行われる簡易な知能検査では「長谷川式簡易知能評価スケール」を使われることが多いです。
これに加え、医師による身体的な検査(尿検査、血液検査、心電図検査、CT画像検査)を行い、総合的に認知症かどうかを判断されます。
法的判断
医学的に「認知症である」という診断結果が出ても、法的には「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではない、という点が大変重要です。
たとえ、認知症を患った人でも法的に効力のある遺言は作成することができる場合があるのです。
「認知症」の人の遺言能力とその法的な判断
認知症だけでなく精神障害などを患って正常な判断ができない場合、その人の状況に応じて青年後見人や保佐人、補助人が付く場合があります。
その場合は、法律行為をする際にさまざまな制限が設けられ、法律行為を行う場合は成年後見人などの同意が必要です。
ただし同じく法律行為である「遺言」に限っては事情が異なり、保佐人、補助人をつけている場合でも、遺書は単独で(保佐人・補助人の同意は必要ない)作成することができます。
青年後見人が付いている場合は「判断能力が一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言をすることができる」と定められています。
つまり認知症でも(一定の条件下で)、法的に効力を持つ遺言を作成することは可能、ということです。
ただしこの状態で遺言を残したとしても、その後に「本当に遺言能力がある状態だったのか?」というポイントについて係争が起こる可能性はないとは言えません。
認知症患者が作成した遺言に関わる裁判では、遺言が法的に有効であると判断された例もあれば、無効と判断された場合もあり、まさにケースバイケースといえるでしょう。
有効・無効の判断の最大のポイントは「遺言能力の有無」にあるのです。
死後の無用なトラブルを避けるには〜遺言書作成の注意点

なるんじゃ面倒だな
小さくできるんですよ
現在認知症と診断が出ている人だけでなく、現在は認知症ではないという人も、この先何が起こるかは不確定です。
終活の一環として遺言を作る時点では、自分が亡くなる日やその時の心身的な状態はわかりません。
遺言作成者の死後に相続人間の無用な争いを防ぐには、遺言作成当時「遺言能力があった」という証拠を、遺言に必ず添えることが大切です。
また、法律的にもっとも強い「公正証書遺言」を作るというのもおすすめです。
遺言能力があることを証明する「証拠」を添える
遺言を作成した時点での判断能力に疑いが出ないように、証拠となるのは以下のようなものがあります。
動画
遺言を作成しているときの、受け答えの様子、遺言者の会話の状況がわかるように撮影します。
また、遺言作成前後の日常の様子なども記録しておくとよいでしょう。
日記・記録
遺言者自身が日々の出来事を記録し、自身の認知や判断能力に疑いがないことを確認できるのがベストです。
遺言者自身が日記をつけるのが困難な場合は、介護をしている人がその様子や会話の様子などをこまめに記録するとよいでしょう。
カルテの写し
遺言作成時に通院している場合は、日付の入ったカルテの写しをもらって遺言に添付しておきます。
作成時前後に、認知症の簡易検査や医師による総合診断を受け、その診断書をつけておけばより安心です。
公正証書遺言を作る
最初の章でも解説しましたが、遺言にはいくつかの種類があります。
その中で法律的に最も覆されにくいのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、遺言者が公正役場へ行って、証人2の立ち会いのもとで遺言を作るというものです。
遺言者が公正役場へ直接いけない場合は、自宅や病院まで来てもらうサービスもあります。
この公正証書遺言は、法律のプロともいえる公証人がチェックして作成する遺言のため、法的に無効と判断されることがありません。
また、本人が役場へ行って作っているため、第三者が勝手に作成したと疑われる余地がなく、作成した遺言書の原本は、公正役場で保管してもらえるため遺言が紛失するというトラブルも起こりません。
ただし公正証書遺言を作成するには費用がかかります。
遺言書に記載される財産の金額によってその手数料は変動します。
費用は掛かりますが、のちのトラブルを回避するには、公正証書遺言はベストの遺言作成法と言えるでしょう。
専門家にしっかり相談する
とはいえいきなり法律の知識もなく、公正証書遺言を作成するのはややハードルが高いかもしれません。
とくに遺言や相続の問題は、とても複雑です。
遺言者を含めた身内だけで話し合いをしても、なかなか具体的には話がまとまらないこともあるでしょう。
そんなときは、法律に詳しい弁護士や司法書士などの専門家を入れて、客観的に整理してもらい、法的に有効な遺言作成の手助けをしてもらうのがよいでしょう。
すでに認知症になったしまった場合
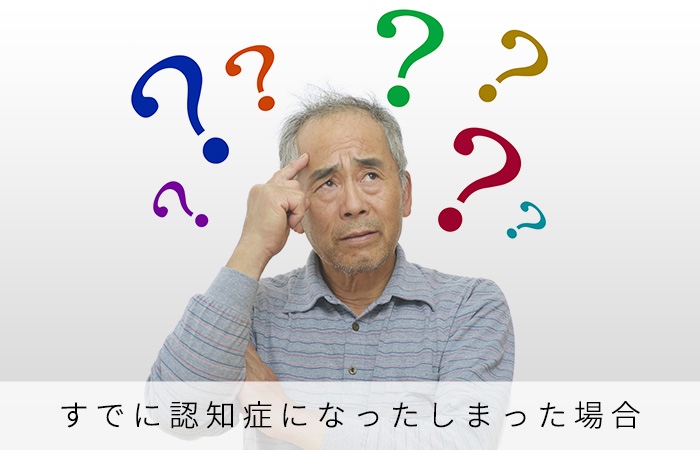
すでに認知症と診断された場合の遺言の書き方について考えてみましょう。
この場合のポイントは、認知症の程度はもちろんのこと、法的には「家庭裁判所で後見開始の審判」を受けたかどうかがポイントです。
後見開始の審判を受ける前の場合
認知症の程度が軽く、意思能力・判断能力は衰えてはいるもののまだ残っているような場合は、通常と同じように遺言書を作成することができます。
後にトラブルにならないように、弁護士・司法書士に相談したり、判断能力があったことを証明する証拠をしっかりとることが大切です。
後見開始の審理を受け、後見人が付いている場合
認知症が進行し、家庭裁判所によって法廷の成人後見人が財産を管理している場合は「一時的に判断能力が回復した」と認められた場合に限って法的に有効な遺言書を書くことができます。
主治医が、一時的な判断能力の回復を認めてくれたら、医師2名の立ち会いのもとで、遺言を作成することになります。
まとめ
遺言作成は、今日から始めても早すぎることはない
かると、少し安心ではないですか?
財産はうまいこと葬式代だけ残してパーッと使い切るのが一番だ、と思ったね
身の回りの整理などの終活は『身体が動く元気なうちに』と焦っても、財産関係を整理して誰にどのように相続させるのかを決める遺言作成は『まだまだ先でもいいか』と思ってしまいがちです。
しかし歳を重ねれば重ねただけ、認知症のリスクが高まることを考えれば、頭がはっきりして認知・判断能力の高い今こそ着手すべき終活のひとつだと認識していただけたのではないでしょうか。
たとえ今、遺言を作成しても、時間が経って事情が変わればそのたびに遺言は作りなおすことができます。
認知症の疑いが出てからあわてるよりも、今日から具体的に考え始めてはいかがでしょうか。
明日、1か月後、半年後、来年には何が起きるかわかりません。
元気で頭がはっきりしている今こそが「遺言作成開始の吉日」と肝に銘じておきましょう。